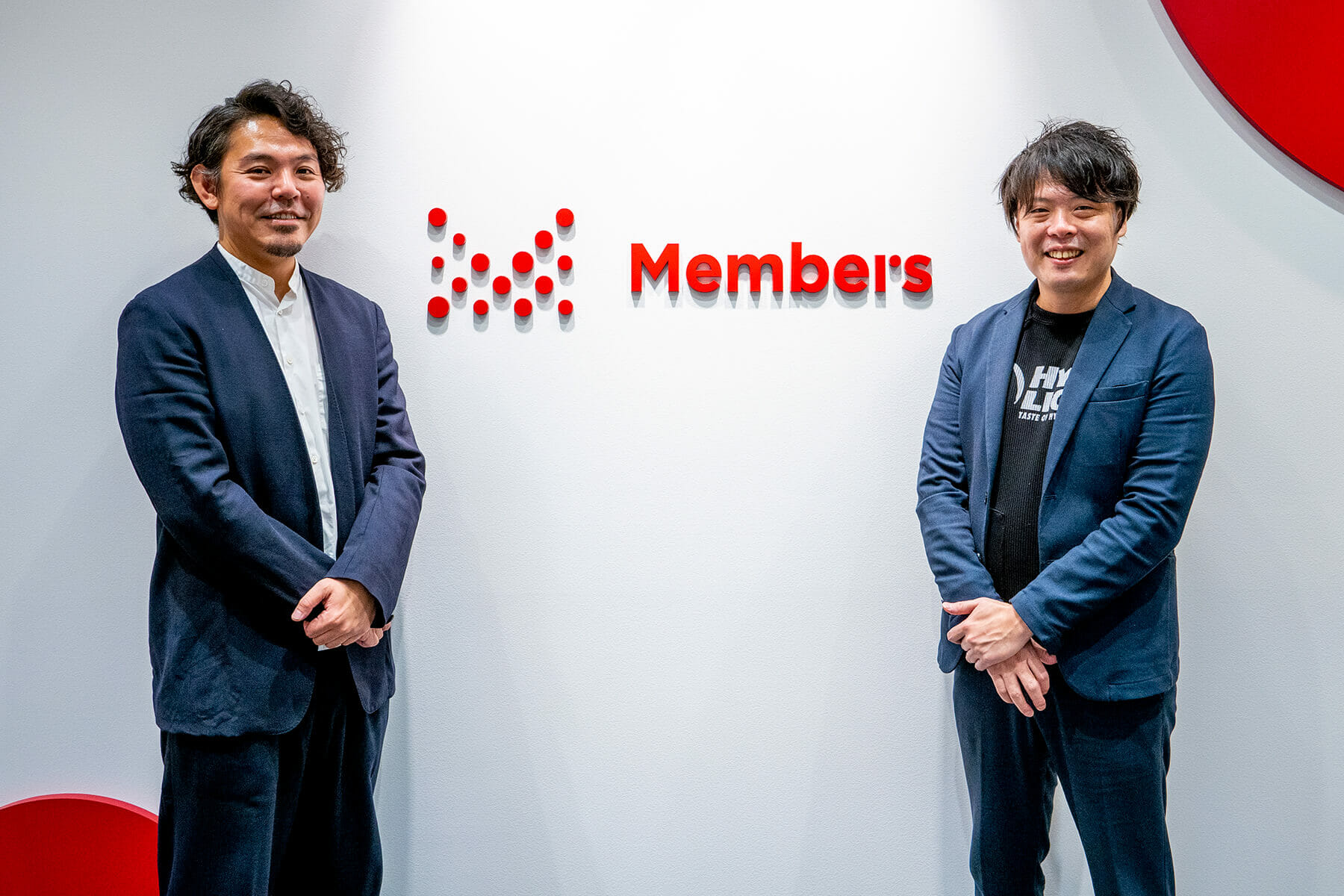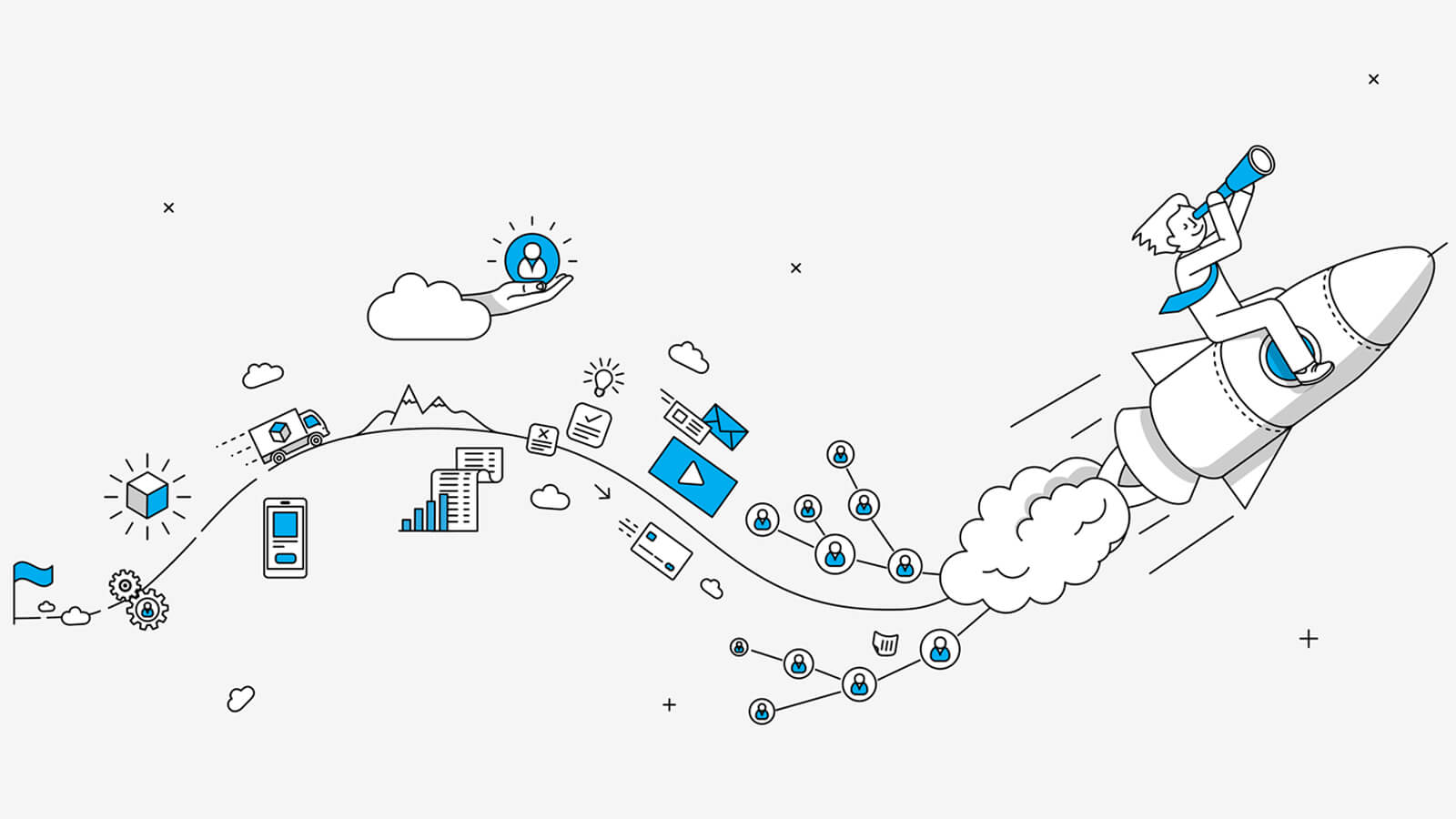インターナルブランディングパートナーとして、人・組織の“ありたい姿”の策定と実現を支援する株式会社ゼロインが、従業員エンゲージメントの高い組織づくりに役立つノウハウをお届けします。
この記事では、コーポレートブランドの策定・浸透サポートやインターナルコミュニケーションのプロジェクトを多数手掛ける三宅が、インターナルブランディングの最前線をお伝えします。
編集部(以下、編):前回の記事「従業員エンゲージメントを強固にする、“ありたい姿”と企業文化のアップデート」では、変化が激しく予測困難なVUCA時代における企業文化の重要性を取りあげました。それでは、企業文化のアップデートは、どのような観点やプロセスで取り組めばいいのでしょうか。
三宅:前回もお伝えしたように、企業文化は、組織の思考習慣や行動パターン、判断基準に影響を与えており、社歴の長い管理職や上司ほど企業文化に染まっているのが実情です。企業文化を変えようとさまざまな手立てを講じても、既存社員が「うちの会社ではこういうものだ」と言ってしまえば、その瞬間に文化はレガシーとしてより強化されてしまいます。
逆に、新しい企業文化の体現者に対して、社内表彰や日常のマネジメントシーンで「それいいじゃん」「もっとやっていこうよ」と共感・称賛される体験をつくることができれば、企業文化を変える潮流となります。つまり、従業員の行動を後押しする「体験のデザイン」が、企業文化をアップデートするポイントであるといえます。体験を無視した表面的な施策・制度だけで社内を変えようとしても、なかなか上手くいきません。
注意したいのは、ひとつの施策や制度の導入で何かが大きく変わることはなく、いきなり大きく変えようとすると、予期せぬエラーや反発を起こしかねないことです。企業文化は、コンピューターを管理・制御するオペレーティングシステム(OS)に例えられますが、OSはさまざまなプログラムが、少しずつ、継続的にアップデートされます。企業文化においても、“ありたい姿”の実現ストーリーに沿った継続的な取り組みが必要です。
その意味では、企業文化は「変革」するのではなく、「進化(アップデート)」や「変化(シフト)」といった考え方が適切です。すでに働いている従業員は、現在の企業文化に馴染んでいる人たちが多いわけで、いきなり真反対の方向性が打ちだされても、「よし、やろう!」とはなりません。一貫した方向性は示しながらも、段階的に変えながら、反応をうかがいながら進めていきましょう。
組織文化のアップデートは目的ではなく、その先にある、ビジョンやパーパスといった“ありたい姿”を実現に導く「従業員一人ひとりの行動を生みだす」ことにあります。そのため、パーパスやビジョンなどの“ありたい姿”を土台に、“生みだしたい従業員の行動”を徹底的にリサーチしにいきます。
“ありたい姿”や目指したい行動は、経営を中心に、管理職から現場で働く従業員まで、さまざまな人が思い描いているので、インタビューや現場訪問を繰り返して知りにいきます。そうして生みだしたい行動を探ってみると、現状からまったくかけ離れたものをつくろう、となることはほとんどありません。現場にはロールモデルとなる、ありたい姿をすでに体現している従業員や、新しいことに挑戦しているイノベーティブな従業員が必ずいます。そうした方々をさらにインタビューしてひも解いていくことで、生みだしたい行動と、その行動を生みだすために必要な企業文化が具体的に見えてくるはずです。
一方で、目指す姿だけでなく「現状はどうなのか?」についても、しっかりと把握することが必要です。現状をどのように感じているのか、何が行動の阻害要因になっているのか、直接ヒアリングすることで見えてくることがあります。
このとき、「企業文化」というテーマで考えてしまうと全体が抽象化してしまうので、最終的に「どのような行動を増やしたいのか」あるいは「減らしたい行動は何か」と、行動を軸に考えるとイメージしやすくなります。たとえば、「異なる部署の人たちが、業務上で部署横断のコミュニケーションをとっている」などです。
漠然と「コラボレーションを増やそう」とメッセージされがちなのですが、抽象的なメッセージを受けて行動できる人は稀です。どのような場面で、どのような行動を起こしてほしいか、具体的な行動をイメージすることで「その行動を生むためにどのような機会が必要か?」が分かるようになります。
そうして具体化してみると、誰に指示されずとも、勝手に部署を飛び越え、周囲を巻き込んでコミュニケーションしている人が見つかるはずです。そうした人にあらためてインタビューすると、その人が当たり前にやっている、行動や習慣が見えてきます。そうすると、次は「その行動を、ほかの人から生むにはどうすればいいか」を考えるることができます。
詳しく聞いていくと、実は上司が経営メッセージを理解できておらず行動の阻害要因になっている、ということも珍しくありません。すると、マネジメント層の研修やワークショップを設計する、という流れができあがります。
このようにして、変化と行動を生みだすコミュニケーション戦略や、戦略にもとづく施策・メッセージなどのストーリーに落とし込んでいきます。
「マネジメント層の研修やワークショップを」といいましたが、変化を生みだすときには明確なコミュニケーションターゲットの設定が非常に重要です。行動や思考を変えていきたいときに、全体を一度に変えることは不可能です。職種や役職、年次など、さまざまなセグメントで分類したときに、どのような層が変化を受け入れ変わりやすいのか、セグメントによって傾向は異なるでしょう。あるいは、どのような層が変わると全社に影響が波及しやすいのかといった影響度や、何がボトルネックになっているのかといった問題意識から、コミュニケーションターゲットを定める必要があります。
変化したくない層を無理に変えようとするよりも、新しいことに挑戦したがっている層から動かしていく考え方もありますし、マネジメントを早期に巻き込んでミドルから順番にやる考え方もあります。自社における、これまでの文脈や特性を踏まえて、コミュニケーション戦略を考えていきましょう。
新しいメッセージを社内に発信する場合は、すでに社内で取り組んでいる機会や場、メディアの有効活用をおすすめしています。社員総会を実施していればワークショップを追加して社員同士で語り合う機会を設ける、社内報があれば特集企画や新コーナーを立ち上げるのもいいかもしれません。取り組みやすいところから始めてみて、少しずつ巻き込みながらつくりあげていくことが大事です。
“あるある”な失敗パターンに、事務局が新しい施策を次々に立ち上げて、「はじまりました!」といきなり現場に投げるパターンです。事務局主導で施策を乱発していると、現場視点からは「また事務局が何かやってる」と、冷めた目で見られることが少なくありません。目新しさは重要ではないので、従業員をいかに巻き込めるかに重点を置きましょう。「何をやったらいいと思う?」から呼びかけ、プロジェクト型で参加しながら主体者になってもらうと、参加者自身が周囲に伝えていくエバンジェリストになってくれます。
かつては、理念や方針はトップダウンで策定されるのが当たり前でした。しかし近年では、“目指すもの”自体を従業員中心で策定するプロジェクトをよく目にします。私たちがお手伝いするお客様でも、ビジョン・ミッションやパーパスはもとより、経営ビジョンのような戦略に近いことまで従業員が策定しています。
VUCAの時代には、トップが計画や戦略を決めても上手くいくかは分かりません。それくらいに世の中の変化は激しく、予測ができないのです。そのときに、変化に応じてみずから考え、行動していく組織には、従業員一人ひとりの「これを実現したい」や「ワクワクする」といった内側から湧きあがる感情が大事になっています。変化に愚直に向き合い続け、継続的な挑戦が必要なため、自分たちが「やりたい」「決めた」というマインドを醸成するプロセスに意味があるのです。
巻き込み型のプロジェクトは、実施前は誰しも腰が重いものです。プロジェクトが始まってからも、これまで考えたことのないテーマについて議論するので、みんなが悩みます。しかし、考える機会を持つことで、会社の事業やビジョン、自分がこの会社でどのように働いていたいかを本気で考え、会社と自分のビジョンに接点を見つけにいきます。そうしてプロジェクトを進めていると、参加している人たちが少しずつ変化してきます。終わるころには、必ず「やってよかった」という話になり、「周囲に伝えていきたい」「浸透施策もやりたい」と言いだします。やはり想いを持ちだすんですよね。
自分の知らないところで決められた“ありたい姿”がトップからおりてきて、「みなさん、こうありたいですよね?」と言われても、なかなか自分のものにはなりません。自分たちでつくる、あるいは、ワークショップの場で内容をかみ砕き、周囲とシェアして会話することで自分のものにしていくプロセスを、ぜひ取り入れてみてください。
この記事の著者

三宅 柚理香
株式会社ゼロイン シニアコンサルタント
1997年からリクルートグループにおいて人材領域を中心に採用広報の企画・制作に携わる。2010年、株式会社ゼロインに入社。インターナルコミュニケーションのコンサルティング、コーポレートブランドの策定・浸透サポートなど多数プロジェクトに従事。現在はシニアコンサルタント 兼 コミュニケーションデザイン総研責任者。